本章では、房総文明における経済システムと企業の働きを見ていきます。現代の様々な文明においては、経済の仕組みがその社会の成り立ちを握る大きな要素になっておりますので、房総文明の成立においてもどのように経済を回し社会を成り立たせていくかという視点は当然大きな意味を持っています。また、2C論より房総文明は日本文明をベースにしたものですから、日本文明におけるコミュニティーどのように房総文明に合わせて捉えなおすかということも大切になってきます。筆者が2章および3章で、会社型コミュニティーが日本文明の現代的価値を代表する最も重要な働きをしていると指摘していたことも合わせて思い出してください。
核となる議論は、房総文明における超価値である「環境と地球を良くするコミュニティー」に対してどうやって「価値」をおけるようにするかということです。価値とは、見返りや報酬を伴った概念ですが、もう一方で社会的評価ややり甲斐・生き甲斐ともリンクしている概念です。この両面を満たすことが、環境と地球を良くするコミュニティーにおいても求められます。
どれだけ環境と地球を良くしたかという評価制度の確立
この点で提案したいのが、房総文明の経済システムには「どれだけ環境と地球を良くしたかという評価制度」を入れることです。これは、ポジティブ・アクションを誘発するために必要な仕掛けです。従来型の、環境の規制、たとえば排ガス規制や農薬の使用制限を思い浮かべてもらえると良いのですが、基本的には環境を汚染するのを最小限にしていこうというネガティブ・アクションで、「環境と地球を良くしているか」という視点は含まれていません。この視点を、房総文明では逆転させるのです。企業や自営業者における製品やサービスがどれだけ環境と地球を良くしたか、それを経済的な評価制度の尺度として導入する、もしもこのことが房総文明では当たり前のことになれば、企業や自営業者は自ら進んでそうした経済的活動に勤しむことになるでしょう。新しい功利的な経済的価値観を構築する必要があるのです。
こうしたポジティブ・アクションを政府による助成金や税制優遇で推し進めるという政策的手段をとる方向性も考えられますが、そうするとそうした助成金や税制優遇を行うための財源を考えなくてはならず、それは社会的なコストとなって市民に結局跳ね返ってきます。できることは民間で、そして自主自律的な経済システムにより自然とこうしたポジティブ・アクションが連続するようにしていかなくては、社会が長続きしません。助成金や税制優遇がなくなったらおしまいになってしまうような弱いものでは、安定して雇用を支え続けられるようなものではないからです。
種式会社とシーズマーケット
経済学の世界では、社会に「市場」という大きな器があって、その中で様々なプレイヤー(民間企業や政府や銀行や消費者など)が存在していると考えます。この章では、そうした経済学の考え方を取り入れていきますが、房総文明においては「環境と地球を良くするコミュニティーに価値を置く」という価値観を持っているために、従来型の企業活動が馴染まない部分も出てきます。「環境と地球を良くするコミュニティー」とは当然ながら、企業や組織、そして自治体も含まれます。であれば、逆に考えると「環境と地球を良くしない」企業や組織、そして自治体は評価されない仕組みになるということであり、価値から来る目的を達成するためには「環境と地球を良くする」企業や組織、自治体が価値を得られるような仕組みを社会が整えていかなくてはなりません。
この点について、本章で筆者が提案したいのが「種式会社」と「シーズマーケット」という新しい仕組みです。
「種式会社」は、「株式会社」と代替もしくは併用される法人格になります。まずは種式会社の具体的中身に入っていく前に、現代日本文明における「株式会社」という制度をおさらいしておきましょう。
国が制度によって法人格を与える株式会社は、その会社の株を買った株主が集まって設立し、株主が株主総会で選任した経営者が経営を行います。この「株」とは英語の「stock」を日本語にしたものです。「在庫=ストック」と現在の日本のビジネスの場面でも使われている通り、ストックはもともと「残っているもの」を指すものでした。人々が集まって何らかのビジネスをして、その結果残っているものを山分け(share)していたことから、その残っているものをもらう権利として、株が成立したのです。ちなみに英語で株主は「share holder」といいます。シェアされる権利を持っている者という意味ですね。今の日本では株式会社の株というと、どちらかという利潤の分け前(=配当)と株式市場での売買差益を目的としたものが大半になってしまっておりますが、原義から言えば株を持っている人が株式会社の所有者だということです。第2章でみてきた通り、株式会社というやり方は明治時代以降の日本で急速に浸透し、経済を回す主導的な役割を果たしてきたのでした。そして、第3章でみてきた通り、それまではうまくいっていた株式会社というコミュニティーが現代日本において少しずつ分裂し、力をなくしていってしまっています。
さて、この株式会社に対する形で提起したいのが種式会社という形態です。株式会社における株と同じように、種式会社の設立については種を買った種主が会社の所有権を有します。「種」とはビジネスの種であり、環境と地球を良くするコミュニティーの目的であり核となるものです。ここで、何を基準にそのような種であることを種主が判断するかは後述します。
株式会社と同じように種主は種を育てることを自らで行うか、または第三者に育ててもらうかを選択できます。ビジネスの種を育てる人が経営者として、ビジネスの種を買ってくれた人に尽くすことは株式会社と同様です。
ここまで理解していただいたのであれば、では種式会社などという法人格を作るのはなぜなのか、という点に迫っていきます。種式会社の種と、株式会社の株の決定的に異なる点は、ビジネスの拡大は種を譲り受けないと行えないということです。現代のビジネスでは、事業の拡大をフランチャイズ型で展開することが多くなっています。何かのビジネス業態で成功した会社を思い浮かべてください。その会社は自己のビジネスモデルとブランドを他社に提供する代わりに、そのロイヤルティーとして代金を回収します。こうしたビジネスモデルをフランチャイズ型と呼びますが、コンビニエンスストアやレストランやドラッグストアやショッピングセンターなど、ほとんどの業態で一般化しているものです。フランチャイズ型が一番消費者の近くに存在するため分かりやすいものですが、フランチャイズ型のようなビジネスモデルは他にもいろいろな産業に無数に存在します。例えば、同じ製品を作る工場を様々な地域に建てることや、工場にブランドと作り方のノウハウを提供して商品を作ってもらうOEMもその例です。また、サービス業に関しては、直営型でありつつも現地支店や現地法人をどんどんと増やしていくようなやり方で事業の拡大を行う方法も多く見られます。こうしたビジネスの拡大方法は現代文明において無数に見られるのですが、房総文明ではこうしたビジネスの拡大はコアとなる「種」を譲り受けないと行うことができないと制限を加えるのです。この制限は、房総文明におけるデジタルガバメントが公平性と公共性を考えながら管理しなくてはいけません。第8章でみてきた房総文明の政府はここで活躍することになります。そして、最も重要なことは、房総文明のデジタルガバメントが、その「種」の数を「環境と地球を良くするか」という視点に基づきコントロールすることです。つまり、環境と地球をたくさん良くしてくれそうな種式会社の種は多く発行を許し、そうでない種式会社の種は発行を制限するのです。こうすることで、補助金や税制優遇などに頼らなくても、ポジティブ・アクションを経済システムに、巻き起こしていけるようになります。
さらに、株式市場(ストックマーケット)と同じように、種を売り買いするシーズマーケットを想定しなくてはなりません。株と同じように、上場した企業の種を投資家が買えるようになります。この時、投資家が考えるのは、そのビジネスの拡大性と成長性でしょう。もし、将来的に環境と地球を飛躍的に良くするようなビジネスモデルの創出に成功した企業の種を持っていれば、そのビジネスモデルを拡大させたい人々に高値でその種を売り渡すことができます。同時に、その種の発行量が重要になります。デジタルガバメントによって評価され、たくさん発行ができる種ほど、たくさんの量を市場で売りさばくことを目論むことができます。したがって、投資家の判断も自然とその企業が「環境と地球を良くする」かどうかに最も重きを置くようになります。このようにして、房総文明における経済はシーズマーケットと種式会社の存在によって回っていきます。逆に、シーズマーケットは投資家からお金を集めるエンジンとなって、種式会社に血液となる財務力を提供します。お互いが両輪になって、房総文明の経済システムは回っていくのです。
房総文明における企業活動と利潤の追求
今度は、経済システム全体というマクロな視点ではなく、民間企業や自営業者というミクロな視点から、房総文明における事業活動と利潤の追求を考えていきましょう。
第7章で論じたように、房総文明はその確立期にいたるまで日本文明に寄生する形で影響度を増やしていきます。2C論より逆襲の文明として機能するためにはディコンポーズ・イノベーション戦略を実行に移していく主体が必要であり、それがまさに房総文明における民間企業や自営業者に期待されます。つまり、現在から未来にわたって、日本文明がイノベーションの結果発生させる文明ごみに対して視点を変えて再利用することを、民間企業が主導的に進めることが求められるのです。
上記で論じたように、種式会社にトランスフォームした民間企業によって、ディコンポーズ・イノベーションを行うビジネスの「種」を発見しそれを育ててもらいます。それがなくては房総文明の経済システムは機能しません。一方で、房総文明の基本的価値観は「環境と地球を良くするコミュニティーに価値を置く」ものですから、そうした価値に貢献できる、もしくは貢献できそうな企業には多くの人が関心を寄せ、種を播き、育てることに協力することでしょう。
また、ディコンポーズ・イノベーション戦略は既存のリサイクルやリユースといった次元をはるかに超えたものになると筆者は考えております。例えば、第7章で例え話をあげた電気自動車とエンジン自動車の例を考えてみて下さい。電気自動車に駆逐されたエンジン自動車のリサイクルやリユースという視点にだけ立つとそれは廃棄される部品を他で使うという視点にしかなりません。しかし、イノベーションの結果排出される文明ごみはそれだけにとどまらないのです。エンジンを組み立てるための機械を作っていたところ、その部品の供給メーカー、エンジンのエンジニアたち、さらにはそうしたメーカーのシステムを作っていた会社や検査システムを提供していた会社も不要になってしまう可能性があります。問題はそれだけでは終わりません。エンジンではなく電気で走る電気自動車ですから、燃料であるガソリンもいらなくなります。そうすると、ガソリンスタンドも当然ながら今ある小売店舗数は必要なくなってしまうでしょう。今度は電気を供給する電気スタンドに業態替えできたらいいのでしょうが、もしそうでない場合、廃業するガソリンスタンドも深刻な環境汚染の原因になる事態になってしまいます。このように、イノベーションの結果に伴って排出される文明ごみに限界はなく、むしろ無限に資源が供給され続けることが予想されます。この問題に立ち向かっていくのが、房総文明における民間企業の役割なのです。であればこそ、民間企業並びに自営業者には、リサイクルやリユースはもちろんのこと、そうした考え方にとらわれない新しくて柔軟な発想のもとに事業を組み立てていくことが求められます。日々の営業により生じた利潤はそうした種をより大きく育むために使用されます。
もしかしたら、農業などの第1次産業と結びつく「種」があるかもしれません。あるいは、床屋さんや美容院、エステサロンなどのサービス業と結びつく「種」もあるかもしれません。さらには、そうした種をうまく育て上げるためにITや金融などの各種産業の「種」もまた必要になってくることでしょう。「種」は無限に考えられます。そして、その種を育てる人たちのコミュニティーこそが房総文明を回す経済システムの根幹であり力の源です。
房総文明とイノベーション並びに起業家
最後になりますが、本章で「イノベーション」と「起業家」の存在について論じておこうと思います。
ビジネス戦略のテキストにはよく「選択と集中」という言葉が登場します。文字通り、限りあるリソース(経営資源)を有効活用するためには、リソースの選択と集中がビジネスの成功には必要であり、全方位的・総花的な事業展開を戒める言葉でもあります。これは房総文明においても同様と筆者は考えています。
まず、ディコンポーズ・イノベーション自体がイノベーションなのではないかという指摘があるかもしれませんが、これは明確に否定しておかなくてはなりません。ディコンポーズ・イノベーションは、自然界における菌や虫たちの働きのように、「発酵と分解」として作用する物であり、「創造」を必要としません。いや、ひょっとすると副次的に、もしくは結果的に、自然界と同じように植物や動物を助ける働きをもたらすかもしれませんが、それが目的となってはいけないのです。そして、房総文明においてはディコンポーズ・イノベーションに集中するため、イノベーションはあくまで日本文明に任せておけば良いというのが房総文明のスタイルです。ですので、イノベーションを起こす起業家というスタイルは、あくまで日本文明側のものとなってしまいます。
しかし、房総文明に起業家が必要ないわけでは全くありません。あくまでイノベーションを起こすような起業家を必要としないだけで、ディコンポーズ・イノベーションを起こす起業家は必要になるのです。このため、房総文明においては新しいタイプの起業家をイメージしなくてはなりません。それは無から有を生み出すようなクリエーターではなく、今あるものでまだ無いことを組成できるような人物像だと筆者は予想しています。ものがあふれ、情報が氾濫する現代社会において、今時代の人々が何を必要としているのかを読み解き、それを今あるものをうまく再利用して組み合わせ提供できるような起業家が房総文明では求められるのです。
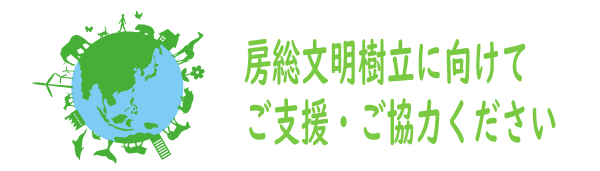 この本の趣旨にご賛同頂ける方はぜひご支援ご協力ください。
この本の趣旨にご賛同頂ける方はぜひご支援ご協力ください。
□ 本をシェアする
こちらのサイトより本をご購入ください(税込み3,300円)
□ 電子書籍を購入する
こちらのサイトより電子書籍をご購入ください(税込み3,300円)
<<前のページへ 次のページへ>>